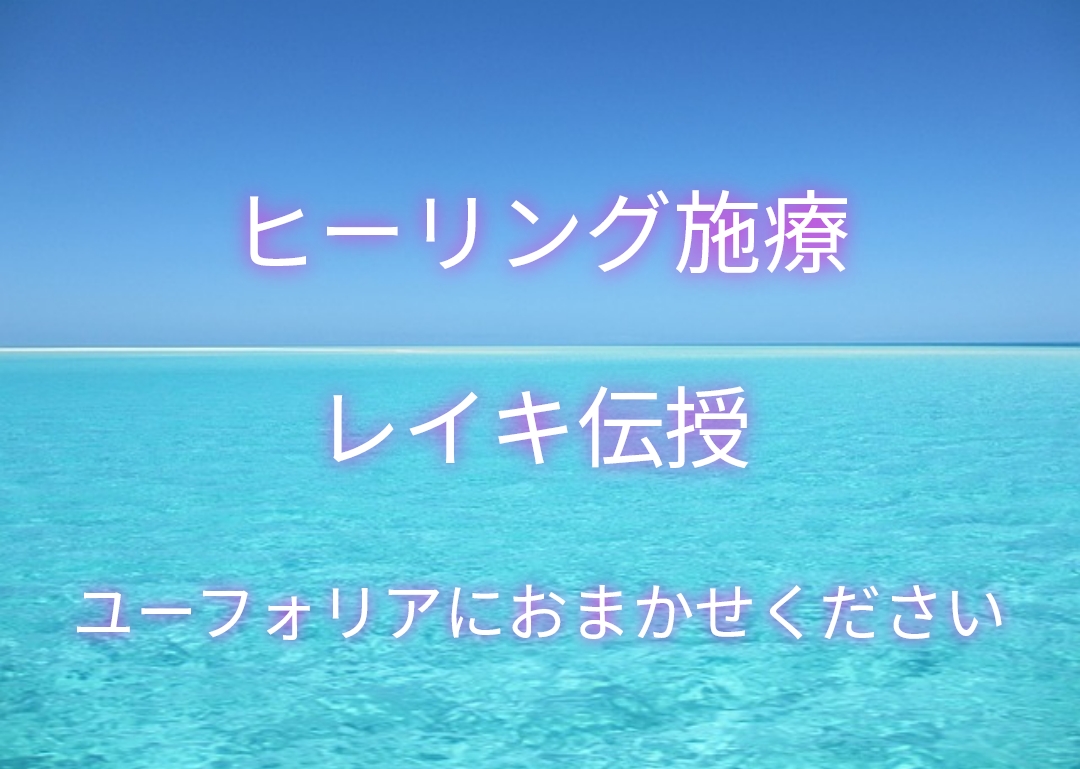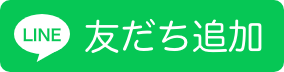普段、このブログでは薬害にあった当人向けに情報発信をしていますが、今回は対象を変えて、
自分の家族が精神薬の薬害に陥ってしまったら、どうすればいいのか?
ということについて書いていこうと思います。
というのも、最近、ベンゾ離脱で苦しい方の家族からの相談が増えているからです。
そういった人は、このあまりにも特異な経験に圧倒されて、どうしていいのかわからず、常に手探りな状態です。
それもそうで・・・家族が精神薬の薬害にあったらどうすればいいのか?主治医含め誰も教えてくれませんし、ネットに情報もないからです。
・・・
離脱について知識をつけよう
まず、離脱の全貌をザックリと理解する必要があります。
これには2つ、読んでいただきたいものがありまして・・・
まずは、アシュトンマニュアルです。
ベンゾ離脱の専門家が書いた文章で、正直賛否両論あるのですが、まずとりあえず離脱の全貌を理解するのにはうってつけです。
続いて、内海聡医師の『心の病に薬はいらない!』という書籍です。
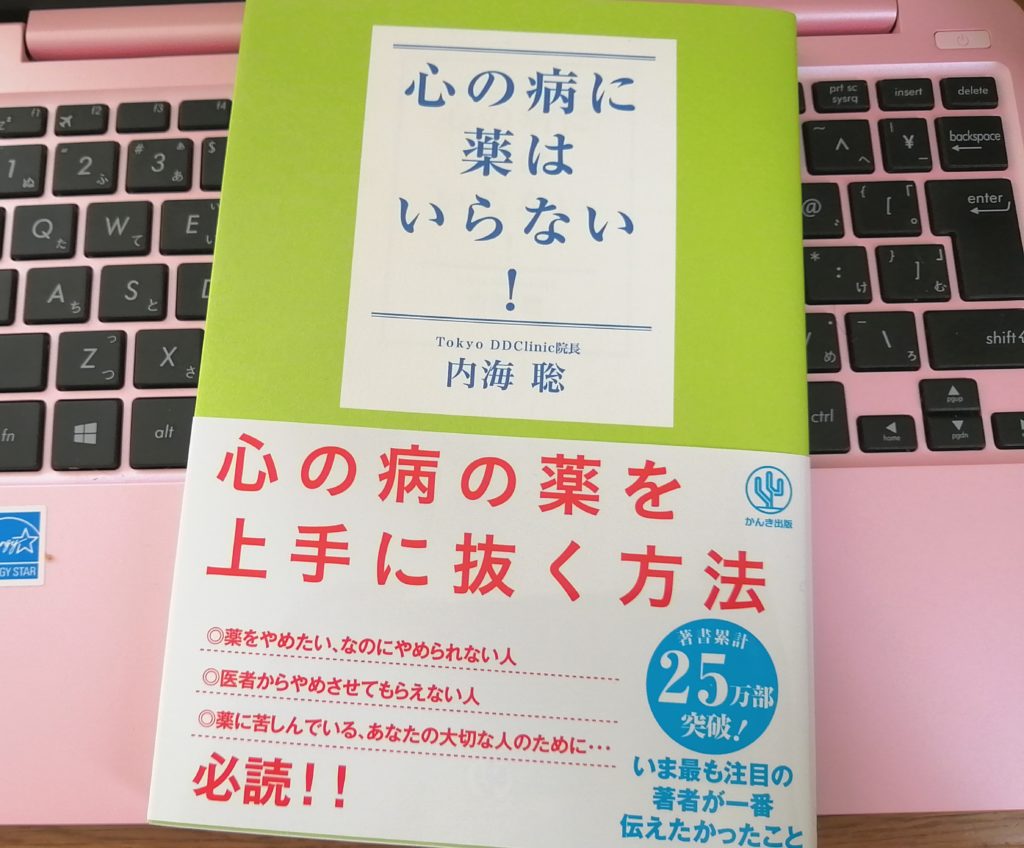
離脱についてはもちろんのこと、精神医療という産業の構造自体について詳しく書かれていてわかりやすいです。
※この2つを読破したら、ぼくのこのブログを読んでもらえるとさらなる知識の補完ができると思います。
・・・
価値判断をせずに、受け入れること
具体的な接し方に入ります。
離脱で苦しんでいる家族を見ると、どうしても、
「〇〇した方がいいんじゃないか?」
「その症状は、〇〇なんじゃないの?」
というように、自分の判断を入れて何か言いたくなってしまいます。
これはやってはいけないことです。
(心配する気持ちがそうさせるのは、十~分わかっています)
できるだけ、自分の意見をいれずに、受け入れてあげるというのがコツです。
ぼくは薬害の当人側だったのですが・・・結局、家族に求めるのは、
「何を言わず、近くにいてくれること」
なのです。
それだけで全然心の持ち方が変わります。
・・・
言い忘れていたのですが、
「ベンゾ離脱中は、あり得ないことが立て続けに起こるもの」
という意識を持つようにしてください。要するに、覚悟してくださいw
まず、症状は本当に意味不明です。
頭痛吐き気などの風邪のような症状もあれば、筋肉痛、ひりひり感、臓器の不快感などが出ることがあります。
ふるえ、けいれん、発作、大量の発汗、脳に電撃が走る感じ・・・こんな症状もあります。
それにさらに加えて、不安感、焦燥感、激怒、現実感の喪失、記憶の欠落、多重人格、希死念慮・・・などなど、心理的症状も加わることがあるのです。
その他、ベンゾ離脱であり得る症状を羅列したら日が暮れてしまうレベルです。
「とにかく奇妙なことが起こる」
これを知識として知って、覚悟することです。
そうすることで、状況に圧倒されるリスクが減ります。
・・・
共感疲れに注意
ベンゾ離脱中の人には、
「自分のことをもっと理解してほしい」
という願望があります。
家族がつらさをすべて理解できるならそれに越したことはないのですが、実際問題、離脱のつらさは離脱になったことがある人にしかわかりません。
つまり、そもそもの話、本人のつらさを理解するのは不可能なのです。
不可能なことを無理にやろうとすると、人間は疲れます。
実際、「共感疲れ」はよくあることなのです。
当然ですが・・・あなたはあなたのメンタルヘルスを維持することが最優先です。
共感するのに疲れてしまって、共倒れしたら最悪なのです。
前でも述べましたが、受け入れること、そばにいてあげることができれば、それ以上の共感は必要ありません。
そもそもの話、いくら共感しても離脱が良くなるわけではありません。
大切な家族だからこそ、線引きが必要だということも理解しておく必要があります。
もし、薬害によって家庭内がめちゃくちゃになったら・・・?
ためらわずに外部に助けを求めてください。
当院にも相談可能です(実績ありです)。

・・・
生活面でのサポート
離脱が激しいと、日常生活もままならない状況になります。
部屋からトイレまで行くのに半日分のエネルギーを使う・・・なんてことも全く誇張なしにあり得る話なのです。
離脱中の家族に対してできる実用的なサポートは、日常生活の手助けです。
食事療法や民間療法など、離脱中にできる対策はあることはありますが、結局いちばん大事なのは「時間が経つこと」です。
いわゆる時間薬ですね。
人間というのは、代わり映えのない毎日を送ると時間の経過を早く感じます。
離脱中は、これを利用します。
要するに、生活をなるべくルーティン化させて、気付いたら1日が終わっていた・・・
という状況を作り出すのです。
たとえば、朝は卵2個のオムレツを食べる、入浴は19時にする、寝る前はYoutubeを見る、22時に寝る・・・など、決めてしまいます。
このルーティン化がうまくいくように、家族の人はサポートをしていただきたいのです。
オムレツを作ってあげるとか、お風呂を焚いてあげる・・・などです。
・・・
補足ですが、離脱中の人に料理を作る際は、砂糖の入れすぎに注意してください。
砂糖は、離脱によって良くないのです。
甘さは、なるべくみりんやフルーツなどでつけ、白砂糖は避けるようにしてください。
ちなみに、アルコールやカフェインなどの刺激物も、脳が過興奮状態になり、発作や症状の悪化を引き起こす恐れがあると言われています。
本人だけで管理できればベストなのですが、離脱の渦中ではなかなかそうはいきません。
「家にあると摂りたくなってしまう」
というのも心理なので、当人が甘いもの好き、お酒好きの場合は、家族もこの際やめてしまうか、それが無理なら外でコッソリ・・・ですw
・・・
まとめると、まずは家族も一緒に離脱について勉強して知識をつけること。
その上で、そばにいてすべて受け入れてあげることです。
ただし、あなたにはあなたの心の健康があり、それが最優先なので、無理に共感しすぎないようにしてください。
実用的なサポートは、生活をなるべくルーティン化させてあげること。食事に刺激物や砂糖を入れないことです。
「共感疲れ」の部分が、正直今回いちばん言いたかったことです。
というのも・・・最悪のシナリオは、あなたが頑張りすぎて家庭自体が壊滅することだからです。
当院では、離脱中の方の家族に対するサポート(カウンセリング中心。ヒーリングも可能。)もできるので、バックにぼくをつけてみるのも、いいと思います^^