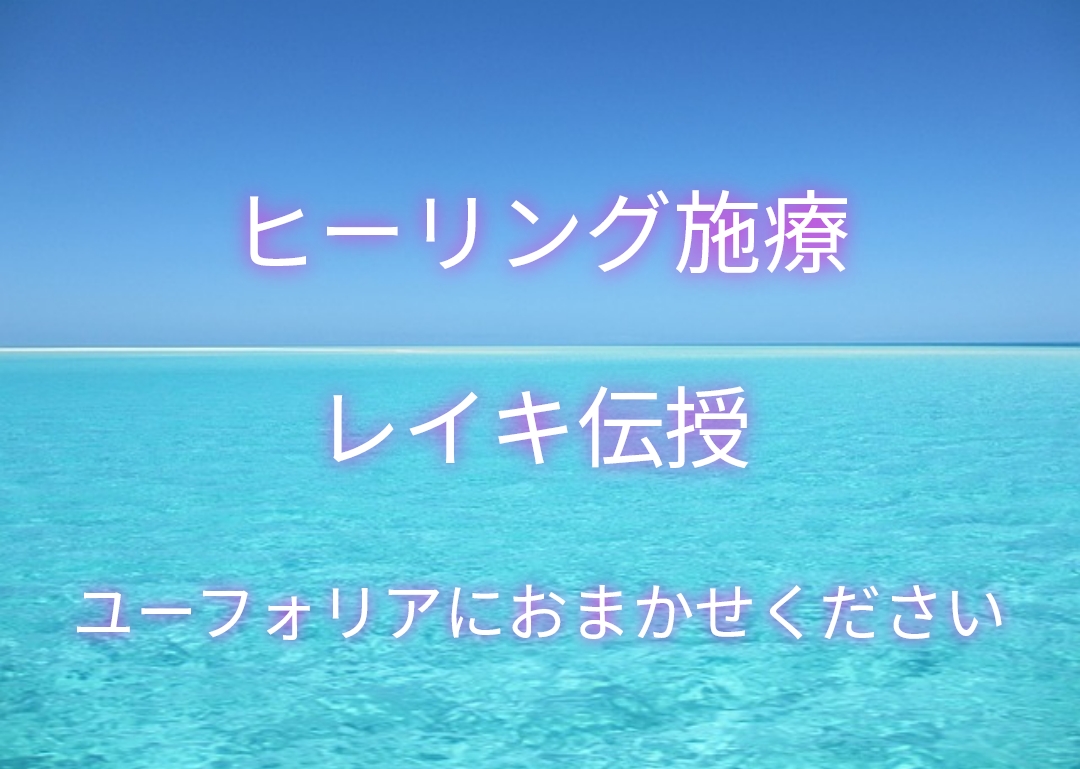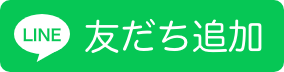最近、毎日翻訳をしています。
イギリスの本なのですが、“Recovery and Renewal”というベンゾジアゼピンや抗うつ薬からの解放マニュアルみたいなのがあって、良い本なので訳しているのです。

無謀にも著者に翻訳許可メールを送ってみたのですが、無視wwwということで、出版できる希望はいまのところかなり薄いのですが、謎の熱意に包まれて作業に没頭しています^^
で、さっきちょうど訳していた部分に「キンドリング現象」というのが載っていました。
これあまり知られていないと思うので、この記事で翻訳部分を抜粋しながらいろいろ書いていきたいと思います。
※以下、黄色で囲った部分は本から抜粋翻訳した文章になります。
・・・
離脱の経験が何度も繰り返された結果起きる神経の状態に「キンドリング現象」というものがあります。
この現象は、前よりも次の離脱の方がリスクが増すというものです。
神経系が過敏になることによって、症状はひとつ前の離脱よりも深刻になるのです。
例を出せば、2回目の離脱は最初の離脱よりも厄介なものになり、3回目は2回目よりも悪くなるという具合です。
これがキンドリング現象。
ぼくはこの本を読むまではこの言葉を知らなかったのですが、現象としてはこういうのがあるのではないかと思っていました。
というのも、ぼくも何回も減薬失敗していますからね。
いちばん「劇的に」失敗したのは笑、レキソタンを3mgから1mgくらいまで減らしてからでした。
1mgにしてから、頭部がとにかくつらくて、頭痛はもちろん、ふわふわして現実感はないし、メンタル最悪だし被害妄想も出ていて、ふにゃふにゃして起き上がれず、常にベッドに顔を沈めていたんです。
工事の騒音に耐え切れず、近くのホテルにいた時に、発狂して救急車騒ぎになりましたw
救急先の医者も当然のごとくクスリ肯定派で、
「注射、打っとく?」
と開口一番言ったのを覚えています。
「兄ちゃん、シャブいのイッパツやっとく?」
にしか聞こえませんでしたね。まさにヤ〇の売人w
結局、シャブいのはイッパツやらなかったのですか(←てかシャブいのってなに?)、レキソタンを2mgまで戻すことにしました。
その後、結局次の試みでも断薬までいけず、その後にジアゼパム置換によってなんとか完全断薬までいけたのでした。
(参考) ジアゼパム置換でレキソタンを断薬できたけど、人にはあまりおすすめできません。その理由。
で、その時にキンドリング現象はぼくの場合は確実にあったと思います。
断薬失敗からの薬を戻す or 加薬すると、次の離脱はもっとひどかったです。

・・・
前に離脱を経験し、現在減薬をしている人にとって、キンドリング現象という概念は大きなストレスになります。
キンドリング現象が起きるのではないかという不安にとりつかれ、最悪の状況に身構えているのです。
SNSなどでベンゾの減断薬をしている人を見ていると、もうどうしようもなくつらい時に、クスリを戻すのかどうか悩む人が多いです。
「せっかくここまで減らしてきたのに、また戻したくない。でも戻さないともう耐えられない。」
というジレンマに陥っているのだと思います。
ぼくは基本的に、
「クスリは戻さない、元の量よりも加薬なんてとんでもない!」
という立場です。
(ぼく自身1回クスリを戻したのですが、救急車騒ぎになるまで意地で耐えていました。)
ものによっては違法薬物よりも依存性の高い麻薬依存から抜け出そうとしているのですから、ある程度の苦痛は仕方ないと思うのです。
苦痛なくやめられた人ももちろんいます。
そういう人が「〇〇という方法をちゃんとやれば苦痛なく離脱を終わらせられる」などと言っているのを見かけたりするのですが、単に運が良かっただけなんですよね。
栄養療法など、優秀な方法はあれど、それは断薬が成功しやすいというだけで、苦痛がなくなるわけではないのです。依存がひどければ、禁断症状は絶対に出てきます。
で、キンドリング現象のリスクも理由のひとつなんですね。
後続の離脱の方がひどくなるということは、失敗のループに陥る可能性もあるので、できれば一方通行で決めたいというわけです。
・・・って、なんか不安にさせちゃいましたかね?
当たり前ですが、減薬している人を不安にさせるのが目的ではありません。
この本では、以下のように続きますが、ぼくも同意見です。
続く内容のあとに、ぼくがこの記事でキンドリング現象を取り上げた意図を書きます。
・・・
私がこの話題についてここで言及したのは、キンドリング現象は経験則ではなくあくまで理論上の話であること、そしてこれらの薬を服用した機会が過去にあったとしても、全員が経験するわけではないということを伝えたかったからです。
反対に、後続の離脱が前のものよりもずっと良かったというケースを私はたくさん見てきています(症状が比較的軽かったという意味です)。
ですから、キンドリング現象を知ったからといって断薬を思いとどまることがないようにしてください。
離脱プロセスがどのように展開していくのかは誰にもわからないことですし、キンドリング現象が起きた人でも、症状にうまく対処して回復しているのです。
・・・と、いうことなんですね。
知識ってのは武器なんですよ。
結局、キンドリング現象を知らなければ、失敗の度に悪くなって、
「なんでひどくなっていくのだろう?もう身体がおかしくなってしまっていて、断薬はムリなのかもしれない・・・」
と思ってしまうかもしれません。
が、知識として知っておけば、キンドリングが出た時に大騒ぎしないで済むと思うのです。
あと、本の内容にある通り、これはあくまで理論上の話なので、全員に起きるわけではありません。
「知識として頭に一応入れておくが、心配はしない」
というのがいちばん良いのだと思います。
ベンゾ減薬関連の知識を調べると、必ずと言っていいほど「脅し」のような不安材料で出くわすと思いますが、すべてこのスタンスで対応すればいいでしょう^^
・・・
対処法はあるのか?という話ですが・・・やはり、これは離脱が出にくいようにする方法全般になりますが、
ゆっくり減らす
ということなのだと思っています。
キンドリング現象に限らず、離脱が本当に激しい人は減薬を急ぎすぎた人です。
ペースが速すぎる
↓
失敗
↓
クスリ戻す
↓
キンドリング現象
↓
次の減薬が困難に
というループが最悪パターンでしょう。
急ぎたい気持ちはわかりますが(ぼくも最初一気やりましたからw)、ゆっくりゆっくりが成功の近道です。
(当院ではレイキヒーリングという民間療法を提供しています。)