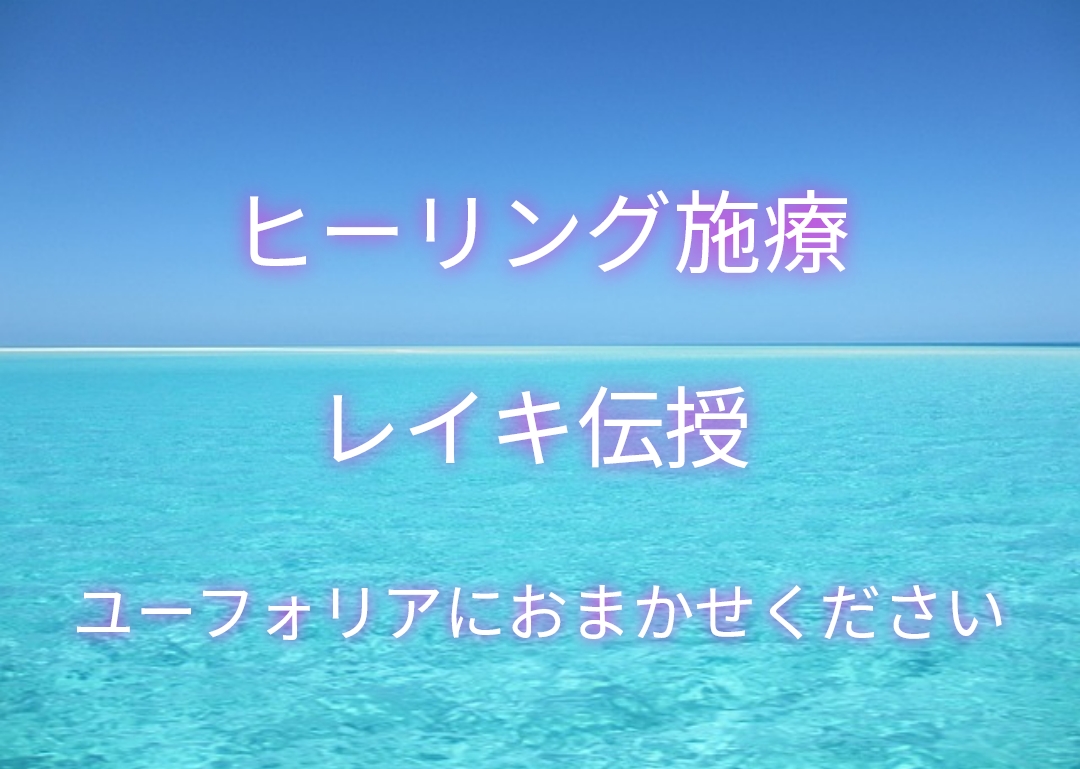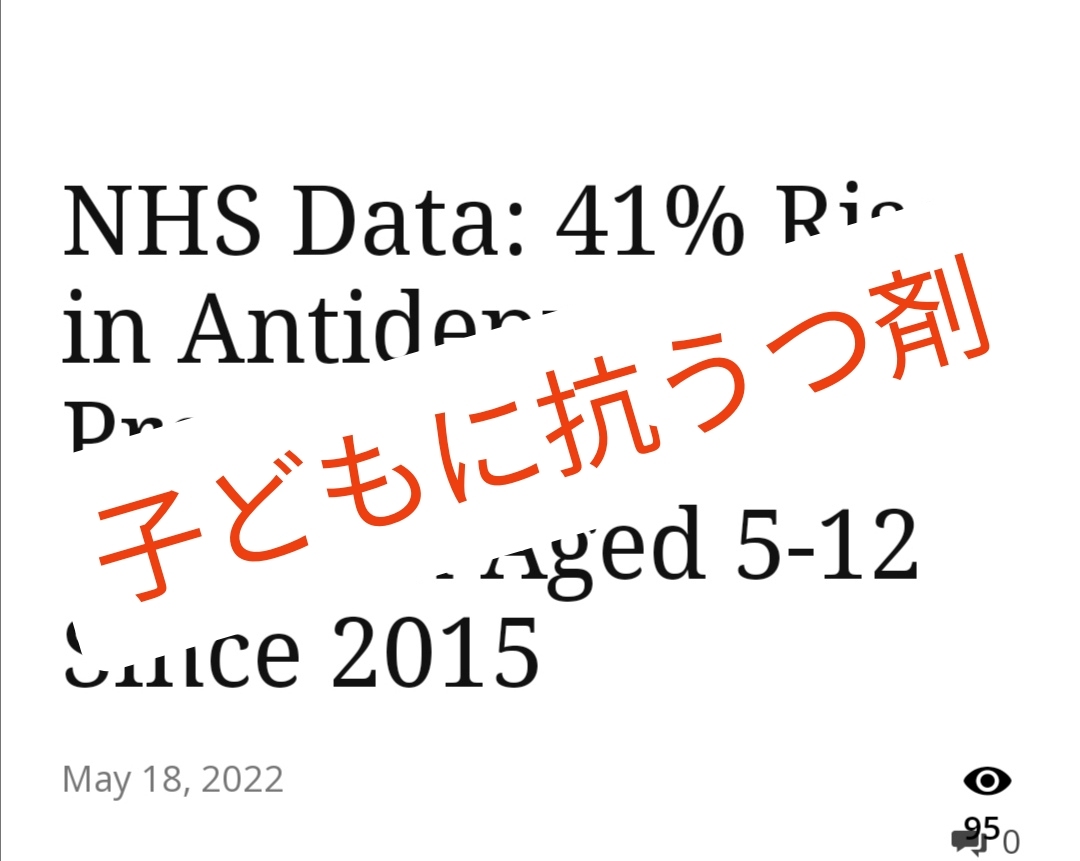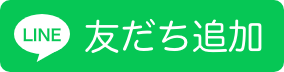ベンゾジアゼピンにはいろいろな種類がありますが、それぞれを比べる際の指標として使われるのが「半減期」と「力価」です。
半減期が長いほど、薬が抜けるのに時間がかかるので、離脱は軽いと言われています。
力価というのは薬の強さです。
一応、この2つが科学的に確かな指標なので、減薬時にはとても有益な情報になるのですが・・・
最近、カウンセリングを続けていく中で、こういった科学的根拠以外にも、それを超えた「何か」があるのではないかと感じています。
・・・
たとえば、メイラックスというクスリです。
高力価のクスリですが、半減期が120時間以上と長く、そういった意味では「わりとマイルド」なベンゾになるのかもしれません。
しかし・・・当院にご相談される方を見るに、どうしてもメイラックスというクスリが悪いベンゾのような気がしてしまうのです。
まず、単純にやめにくいです。
漸減でスローペースでやっていっても、激しい離脱が起きて、また再びベンゾの沼に引き戻されてしまうパターンが、他のベンゾよりも多い気がしています。
もちろん、うちに相談に来る人の範囲なので、数十人レベルの・・・データとも言えないものなのですが、ネットを見ていても、やはりメイラックス断薬で苦労している人は多いようです。
離脱自体も・・・ベンゾ離脱はどれもあり得ないくらいシンドイのですが、メイラックスはその中でもキツイ上に、特有の謎の症状が出る・・・と言ったら違うかもしれませんが、あるクライアントさんから、
「こういう症状があるんです」
とあまり聞かない症状を聞いて、また別のクライアントさんから、
「〇〇みたいな症状が出るんです」
聞いてみたら、二人ともメイラックスだった。
もしかしたら、これはメイラックスで出やすい症状なのか・・・?
みたいなことがあるんです。
(顧客情報に関わるので、具体的にどんな症状なのかは書けませんが、とにかくそういうことがあるのです。)
・・・
以前、Youtubeに「リボトリールというベンゾが特にヤバい」という動画を出しました。
リボトリールと並んで、メイラックスはやっかいなベンゾに入る気がします。
(まだぼくもデータ集め中なので、はっきりとは言えませんが、おそらくそうなのでしょう。)
・・・
ぼく自身の経験を話すと、最初に出たベンゾはレンドルミンでした。
レンドルミンは、半減期が約8時間と、短いベンゾなので、離脱が急速でやめにくいと知られていますが、ぼくは依存はなく、一気にやめて何も起こらなかったのです。
続いてデパスが出ました。
高力価、短期型ということで最悪のベンゾのひとつなのは間違いないですが、これもぼくは簡単にやめられました。
しかし、数年後に出たレキソタンという薬がダメだったんです。
レキソタンは、力価は高くなく、半減期も中期型で、多くの人にとって比較的やめやすいベンゾになりますが、ぼくには最低最悪のベンゾだったのです。
わけのわからない離脱症状のオンパレード。
キラキラと周りがミラーボールのように輝く幻覚作用まで出て・・・
いままで一般的には危険なベンゾが大丈夫だったのに、その逆のベンゾがバッチンはまってしまったわけです。
何度も減薬に失敗し、結局ジアゼパム置換(アシュトン・メソッド)によってやっと完全断薬できたのです。
・・・
さて、この記事のタイトル「半減期や力価を超えた”何か”」ですが・・・その「何か」って、いまのぼくの体験談からわかるのは、
個人の体質その他による反応の違い
があるのだと思います。
要するにキャラクターですね。
統計をとったら、科学的根拠通り、デパスやレンドルミンの方が被害が大きいのかもしれませんが、ぼくはレキソタンがもう最低最悪の相性だったのです。
・・・
さて、「何か」の正体にはもうひとつあると思っています。
つまり・・・そのクスリ自体が、もう欠陥品というか、
「アカンくすり」
ってことです。
はっきり言うわ。リボトリールとメイラックスです。
メイラックスに関しては、半減期という、離脱を予測する上で重要な指標を無視してヤベェわけですから、
もうなんかクスリとしてこれなんかもうアレなんじゃねぇの?
ということです。
部分的に、種類規制をすべきなんじゃないのかなぁ。
・・・
最後に・・・お医者さんは、ほとんどがベンゾについてよくわからないか、わかっているけれど減薬断薬指導は金にならないからやりたくない人です。
で、中には理解がある人もいますが、ひとつ罠があります。
お医者様ってのは、この国でいちばん勉強ができる人がなりますから、データや科学的根拠を妄信する傾向があります。
そうなると、
「半減期の長いメイラックスに変えましょう」
みたいな話になるわけです。
また、患者本人は離脱でものすごくつらい上に、クスリ自体に疑問を抱いていたとしても、
「そのクスリは半減期が長いから、そんなにつらくなるのはあり得ない。薬のせいじゃないよ。」
などと平気で言ってしまったりするのです。
要するに、本人が感じている感覚、ひとりひとりが違う感覚というものを考慮に入れず、じっくり考えることなしに、話もろくに聞かず、データや科学的根拠で上からフタしてくる場合があるということです。
まず、医者はこれやるのやめろ。患者が絶望するから。な?
そして、患者さんで、そこら辺のコミュニケーションでズレがあってきつい場合は、ぼくに相談してください^^